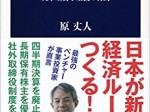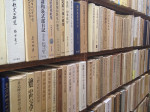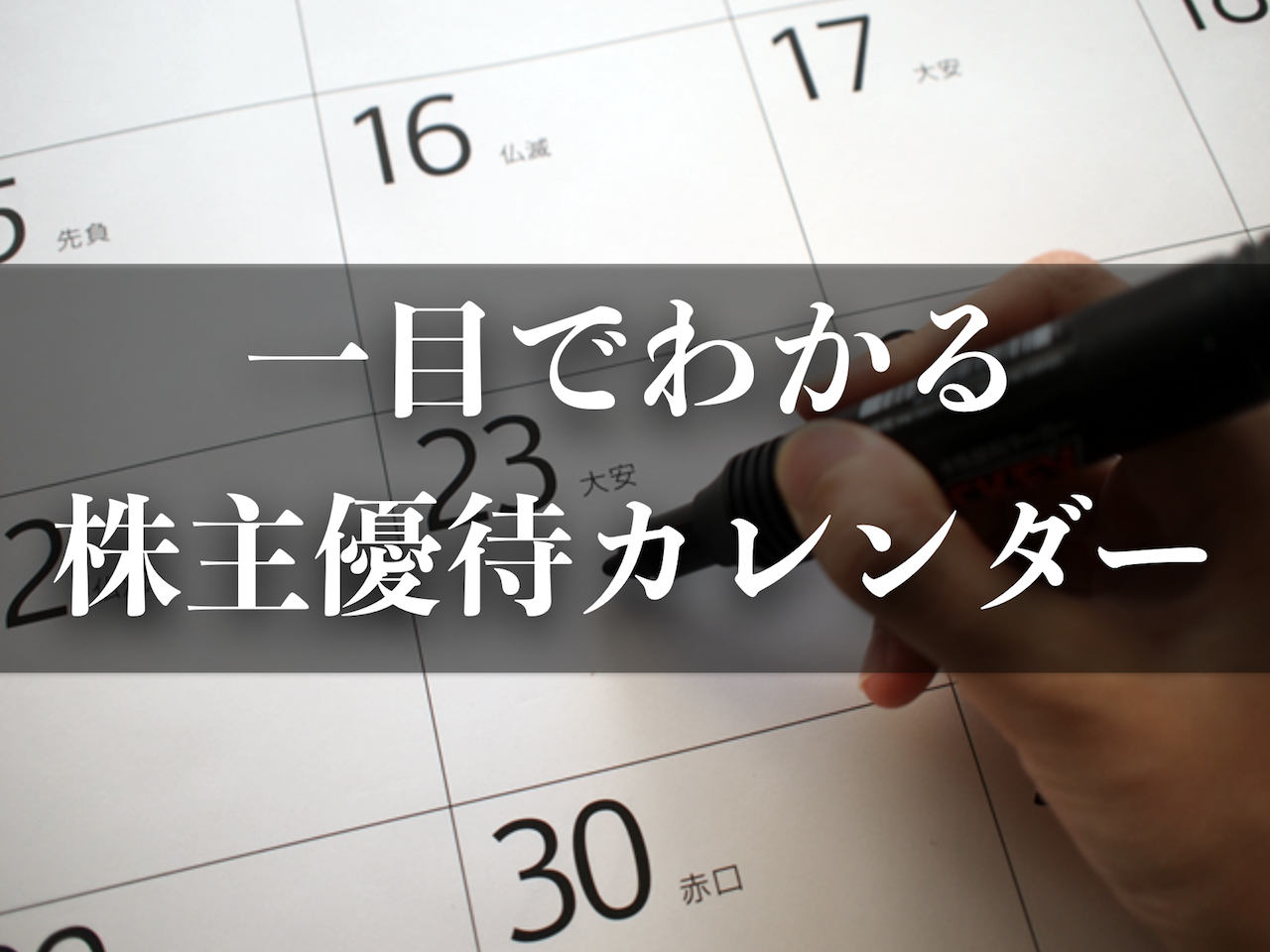元BCG外資コンサルが語るニュースの読み方!「相関」と「因果」の違いを知る
- 2016/10/25
- ビジネス

今の時代だからこそ覚えなくてもいいけど、理解しておきたいことがあります。
今日はそんな相関(関連性)と因果関係の違いについてのお話です。
相関と因果関係をはき違えた市長の話
ある大都市で犯罪が問題になっていました。
警察官の数も増えつづけ財政を圧迫。
そこで、ある担当者が調べると、警察官の数と犯罪の数には強い相関があることがわかりました。
この時担当者が持ってきたグラフは、X(横軸)=警察官の数、Y(縦軸)=犯罪数となっていました。
これを見た市長は、「そうか警察官の数を減らせばいいんだ!」と手を打ったとか。
このレベルになるとさすがにいやいやそれは違うんじゃと思う人も多いと思います。
ただ、これ何が問題かちゃんと説明できるでしょうか?
相関グラフは「どう読むか?」が大事
相関を調べることは実はExcelを使えばすごく簡単。
Googleで第2次世界大戦の終戦の年を調べるのと同じくらい簡単にグラフを作り、相関係数を導くことができます。
ただ、このグラフを「どう読むか?」という判断能力がないと情報が多いこの時代だからこそありえないようなミスをする可能性を秘めているのです。
(誰でも簡単に相関グラフを作れるのでもっともらしく聞こえてしまいます。)
「過労が問題→労働を減らせ」は正しいか?
例えば、某企業の社員自殺について流れてくる報道を考えて見ましょう。
「超過労働が問題だ。だから労働を減らせ!」というのは
正しいでしょうか?
超過労働時間をX軸、会社での鬱発生数をY軸に取ります。
するときっと、相関があるはずです。
すると、超過時間を減らせばいいという考えが出てきます。
しかし、おそらくそれでは問題解決にはなりません。
なぜなら、因果関係を見誤っている可能性があるからです。
今回のケースでは、その業界に対する顧客の態度、業務依頼など商習慣を変えなければ、問題は解決しない可能性が高いと思います。
ただ残業時間にキャップをもうければいいと言うのは対応とは言えません。
例えば、金曜の夜に、「月曜の朝までにこれやっといてくれ。」と上司に言われて、「あ、僕帰ります残業規制があるんで。」と言ったらどうなるでしょうか?
きっとその仕事は下請けの会社に流れるだけです。
そうすると、大手企業ではたとえ問題解決したように見えても、下請けで同じ問題が起きることになります。(たぶん、もうすでにたくさん実際には起きてるけども、それは見えてないだけで、さらに状況は悪化することになる。)
今回ニュースになったことでその場しのぎの対応をしていては、結局何も解決していませんでしたということになる可能性があるんですよね。
こういう報道って意外に多いんです。
現代の私たちに求められていること
ニュースを見た時に、報じられていることを鵜呑みにするのではなく、それって本当に因果関係はあるのかな?相関があることと勘違いしてないかな?という判断が一人ひとりがしっかりできるようになることが求められている時代だと思います。
情報はあふれるほどある。
それをどう取捨選択し、どう使うかは個人に求められている時代なのです。