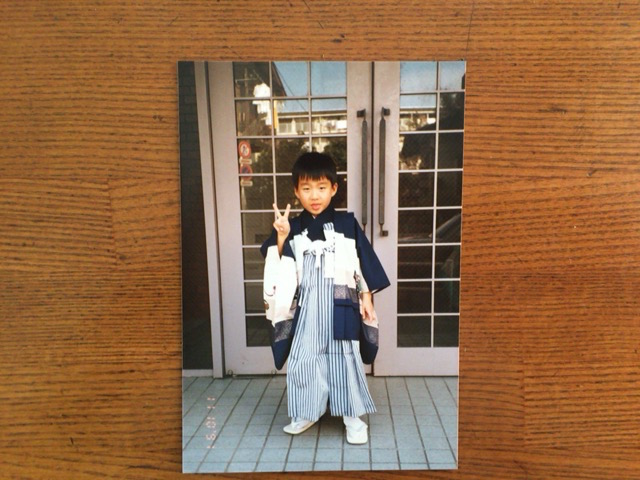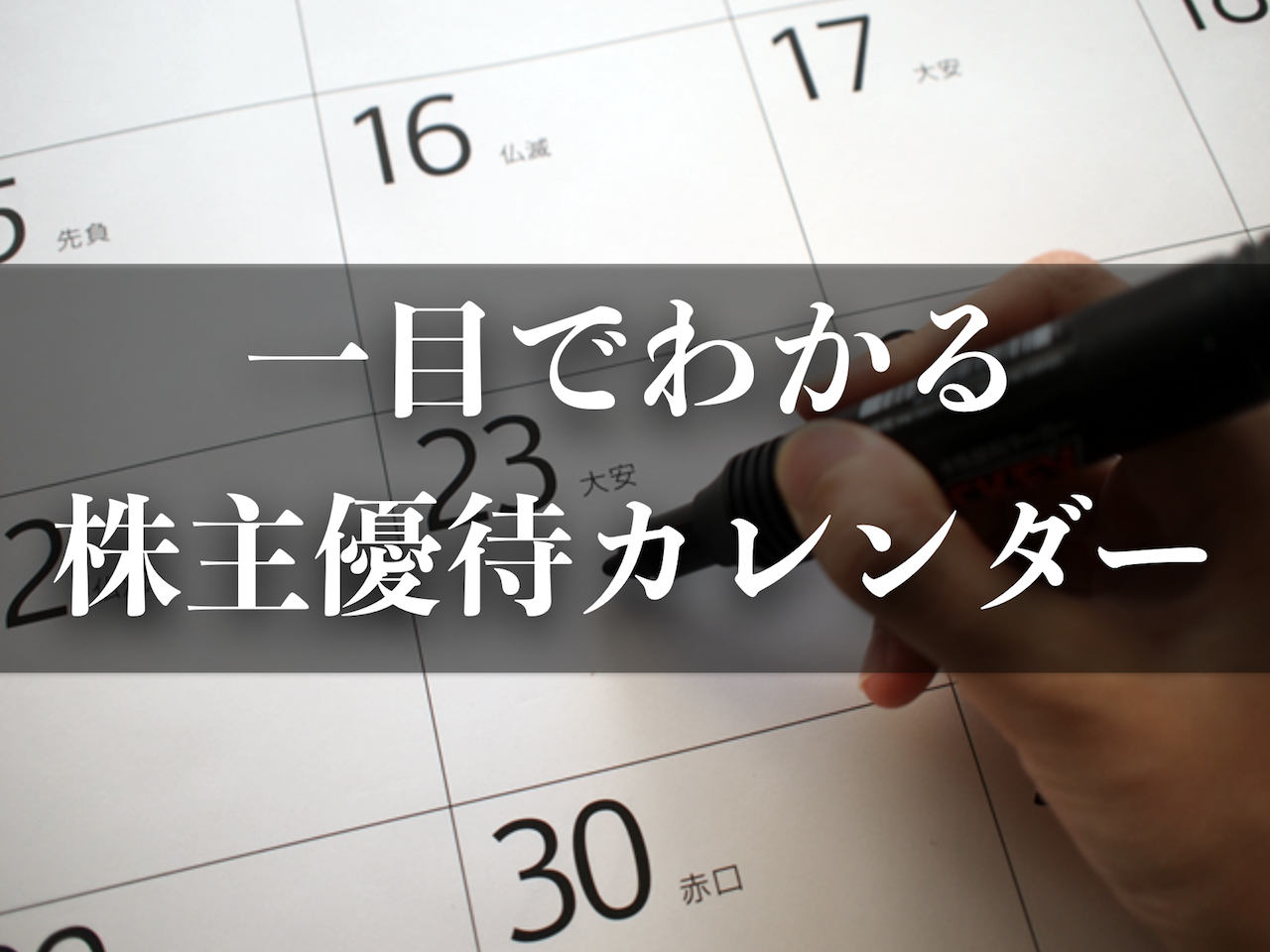富田博之「普通の大学生だった私がミャンマーで就職した理由」(前篇)
- 2015/9/29
- ライフスタイル

ミンガラバー。(ミャンマー語でこんにちは)
私は約2ヶ月前から、アジア最後のフロンティア「ミャンマー」の都市ヤンゴン(旧名ラングーン)で、日系IT企業の現地採用でミャンマー支社長代理として、働いています。
初投稿なので、今回は私の自己紹介を書いていきます。
高校まではどこにでもいる普通の学生だった
私は1986年に西東京市に生まれ、埼玉県所沢市で育ちました。
小学校、中学校、高校は全て県内の公立の学校に行きましたが、
学業並・スポーツ並で特筆すべきことは何もなく、生徒会や文化祭や体育祭で活躍することもなく、当然クラスで人気者になったことも(当然モテたことも)ありませんでした。
今振り返っても、地味などこにでもいる学生でした。
高校に入っても、グレるような反抗心はなく、最も尖っていた時は、たしか髪を茶髪にしていた位。笑
高校と言えば年齢的にお年頃ですが、男女共学の学校にいながら、もっぱら自分と同じような「影薄い系男子」とツルんでいたので、
「あれ?今週女子と喋った記憶ないな」という状況で、高校時代は特に自分の「黒歴史」だと思っていて、あまり人に話したことがありませんでした。
大学進学からはどこにでもいる海外大好きな普通の学生だった
都内の大学に進学してからは、それまでの受験勉強漬けのガリ勉生活の反動からか、好奇心が爆発しました。自分の興味のあることに片っ端から、
首を突っ込み、軽音楽に始まり英会話、オールラウンド、フットサル、ボランティアとサークルのハシゴをしていました。
その中で、自分の好奇心を最も満たしてくれたのが、国際交流サークルでした。
海外の提携先大学から、定期的に来日する交換留学生と、英語もロクに喋れなかったのにBBQをしたり、旅行に行ったり、留学生たちの家でパーティしたりして、交流していました。
留学生たちに刺激を受け、19歳の時に初めて海外(オーストラリア)に行ったことを皮切りに、その後も「大学生活と海外」は切っても切り離せないものになりました。
アジアに目を向けたのはゼミナールに入ってからで、当時サークルのリーダーだった、日英バイリンガルの先輩(男)に憧れて、その先輩がリーダーを務めていたゼミナールを志望したのが、私とアジアとのきっかけでした。
ベトナムだけでは飽きたらず大学を休学して世界旅行
私が所属していたゼミは、環境経済と開発経済が専門で、毎年【アジア・インターンシップ】と銘打ち、ベトナムのハノイで現地調査と現地学生との討論会をしていました。
その時ベトナムで見た、東南アジア特有の熱気や、成長する国の現状を見せつけられた当時の私は、居ても立っても居られず、このまま周りの学生と同じように就職活動することに疑問を感じ、大学4年時から休学。
周りには知見を広めると言って、半年間かけバックパック一つで、アジア・アフリカ・中東を旅していました。今考えると、フラフラしていただけなのですが、その世界旅行の経験も含め、大学生活に「外の世界」に触れたことが、どうも今の自分を作っているようです。
就職活動中100社の企業を受けて感じた海外就職がスタンダードではない日本
無事に帰国したのもつかの間、旅行中に起きた08年のリーマンショックの影響で、世界の景気は一気に冷え込み、漏れなく日本の新卒採用活動も、
何度目かの氷河期を迎えていました。
休学して海外でフラフラしていた私にも、ご縁があり結果的に就職することはできたのですが、就職活動中に受けた企業の数は全部で100社。
嘘みたいな話ですが、本当に100社目の企業で、内々定を頂きました。
フラフラしていたツケとして、全ての責任は自分にあったのですが(笑、来る日も来る日も「お祈り」メールばかりで、本当に苦しい就職活動でした。
その就活時に思ったことが、「何でわざわざ日本で就職活動しないといけないんだろうか?」という疑問でした。
日本人が日本で働くのは当たり前と言えば、当たり前な話なのですが、「海外で働くという選択がもっと当たり前に用意されていたら、自分はこんな苦しい思いをしなくて済んだんだ!」と(笑。
誰にもぶつけられない、負のエネルギーが心の内に、蓄積されていました。
その負のエネルギーは、就職活動終了と同時に消化されたように見えましたが、そうではありませんでした。
(後編に続く)